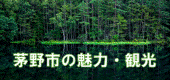情報をさがす
キーワード検索
ページID検索
本文
【御柱祭】上社里曳き フォトギャラリー
令和4年5月3日、4日、5日 上社里曳き
晴天に恵まれた5月3日、上社里曳き初日を迎えました。
4月に行われた山出しは、新型コロナウイルス感染症拡大防止によりトレーラー搬送で行われましたが、マスク着用や定期的な「めどでこ」・「曳き綱」のアルコール消毒、曳き綱に括り付けた「小綱」の自己管理制等、各柱ごとに感染拡大防止対策を取りながら人力での曳行が行われました。
午前7時30分、諏訪大社本宮に建てられる本宮1~本宮4の4本の柱が次々に御柱屋敷を出発。
諏訪大社上社境内に柱を曳き付ける本宮の柱4本は、曳行距離およそ2.4キロを2日間かけて曳行します。
出発してすぐに迎える最初の難所箇所、「安国寺」信号機を直角に曲がる場面では、信号機の高さまで到達する「めどでこ」と呼ばれる、御柱の前部と後部に穴をあけてV(ブイ)字形に取り付ける木の柱に乗った氏子らが「よいさ、よいさ」と威勢のいい掛け声をかけ、柱を曳く氏子たちは喇叭(ラッパ)演奏にあわせて力強く柱を曳きました。
2日目は、上社前宮に建てられる前宮1~前宮4の4本の柱が午前7時30分に御柱屋敷を出発。
前宮の柱は、およそ1.3キロメートル離れた上社前宮を目指します。
前宮境内入口から長い急坂を上る最大の難所を「協力一致」で一気に駆け上がる様子は、圧巻でした。
諏訪大社上社境内に向けて1日目から曳行が続く本宮の4本の柱は、氏子たちが力と技術を結集させて鳥居をくぐり抜け、最後の難所「階橋の石段」を越えると、大きな拍手が起こりました。
最終日は、8本すべての柱で建御柱が行われました。
本宮の柱では午前中に柱の先端を三角錐に切り落とす「冠落し」が行われ、「斧」(よき)で丁寧に削られました。
午後から始まった建御柱では、柱が徐々に垂直に立っていく様子を、氏子らは柱を見あげながら喇叭や木遣りの演奏に合わせて「よいさ、よいさ」の掛け声とともに、かたずをのんで見守りました。
地区の旗持ちをしている氏子は、「よいてこしょ、よいてこしょ」と竹でできた支柱を地面に力強く打ち付け、氏子の安全第一と建御柱の成功に気持ちを込めました。
午後6時までには本宮・前宮それぞれの境内の四隅に御柱が立てられ、3日間のフィナーレを迎えました。