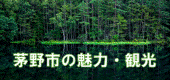本文
戸籍に関するよくある問い合わせ(FAQ)
Q1:家族が亡くなり、銀行の人に「ジョセキトウホン」を取ってくるように言われました。
Q2:家族が亡くなり、相続や保険、自動車の処分などの手続きを進める必要があります。どんな戸籍を取ったらいいですか?
Q3:出生~死亡の戸籍を取ってくるように言われましたがどうしたらいいですが?
いくら用意したらいいですか?
Q5:親が茅野市に戸籍を置く前の、県外の戸籍を取得したいのですが。
Q8:本籍地が遠方なので窓口に行くのが大変です。電話やメールで取得できますか?
Q12:親子であるという証明をするために何を取ればいいのか。
Q1:家族が亡くなり、銀行の人に「ジョセキトウホン」を取ってくるように言われました。
亡くなられた方の除籍謄本をお出しする場合、亡くなった方のどのような事柄を証明するかによって内容が異なります。
大まかに分けて下の2つに分かれます。
- 亡くなられた方の死亡の記載がある戸籍(亡くなられた事実を証明)
- 亡くなられた方の出生から死亡までの記載がある戸籍(相続人を確定する証明)
1が必要な場合は、亡くなられた方の最後の本籍地で除籍謄本(戸籍に記載されている方が全員除籍になっていない場合は戸籍謄本)をとることで死亡の記載のある戸籍を出すことができます。
2が必要な場合は、生まれてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍を出す必要があります。戸籍は、婚姻や転籍、法の改正などによって作り変えられるため、出生から死亡までの戸籍が必要な場合は複数個の戸籍を出す必要があります。金額も人によって異なるため、戸籍をお出ししてからのお伝えになります。
Q2:家族が亡くなり、相続や保険、自動車の処分などの手続きを進める必要があります。どんな戸籍を取ったらいいですか?
それぞれの手続きによって必要な戸籍が異なりますので、提出先にどのような事柄の証明が必要か事前にご確認ください。(亡くなった事実・親子関係・生まれてから亡くなるまでのすべて など)
相続の場合、亡くなった方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を必要とすることがあります。
Q3:出生~死亡の戸籍を取ってくるように言われましたがどうしたらいいですが?
いくら用意したらいいですか?
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍をお取りいただく場合、戸籍証明書等交付請求書のご記入をお願いしております。その際に亡くなられた方の本籍地・筆頭者のお名前が必要になります。
出生から死亡までの間に法律の改正・結婚・離婚・転籍等により戸籍が変わりますので、お客様によってお出しする戸籍の通数が異なるため、手数料も異なります。お支払いいただく金額は戸籍をお出ししてからのお伝えになります。
Q4:直系親族以外の戸籍を取得したいのですが。
戸籍謄本等を請求できる方は戸籍に記載されている本人、またはその配偶者、直系親族(両親・祖父母・子・孫)に限ります。
直系親族以外の戸籍(例えば兄弟姉妹の戸籍)が必要な場合は、第三者としての請求となります。
Q5:親が茅野市に戸籍を置く前の、市外の戸籍を取得したいのですが。
令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付が始まりました。最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。また、郵便で本籍地に請求することも可能ですので、必要なものをご用意のうえ、該当の市区町村に請求をお願いします。
戸籍証明書の広域交付についてはこちらのページをご覧ください。
郵送による戸籍の請求についてはこちらのページをご覧ください。
Q6:本籍がどうしてもわかりません。
本籍がわからない場合、次の3つの方法でお調べいただくことができます。
- 親や配偶者に聞いていただく。
- 本籍を記載した住民票を取っていただく。(1通300円)
- 警察署または免許センターで調べる。(運転免許証をお持ちの方に限ります。)
なお、お電話や窓口ではお答えいたしかねますのでご了承ください。
Q7:自分の戸籍の筆頭者を知りたいのですが。
筆頭者は戸籍の一番上に名前が書かれている方になります。
未婚の方であれば、ご両親の内、結婚前から苗字が変わらなかった方の方になります。
ご結婚されている方であれば、ご自分と配偶者の方の内、結婚前から苗字が変わらなかった方の方になります。(例:結婚後、夫の氏を名乗っていれば、夫が筆頭者になります。)
なお、筆頭者は亡くなられても変わることはありません。
また、自分の戸籍の筆頭者は、自分の住民票を取ることでもわかります。住民票に「本籍・筆頭者名を記載する・記載しない」を選択していただく欄がありますので、「記載する」に「丸」をお願いします。
Q8:本籍地が遠方なので窓口に行くのが大変です。電話やメールで取得できますか?
令和6年3月1日より戸籍証明書の広域交付が始まりました。最寄りの市区町村窓口で戸籍証明書を請求できるようになりました。
戸籍証明書の広域交付についてはこちらのページをご覧ください。
また、郵送で請求することもできます。戸籍証明書交付請求書(郵送用)を記入して頂き、手数料、返信用封筒、請求者の本人確認ができる書類(運転免許証など)のコピーと共に本籍地の市区町村役場にお送りください。手数料は定額小為替または現金書留でご用意をお願いします。証明書の手数料は市町村によって異なるため、電話やホームページなどでご確認をお願いします。
郵送による戸籍の請求についてはこちらのページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニのマルチコピー機で戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、住民票などの証明を取得することができます。(実施していない市区町村もあります)
マイナンバーカードによる各種証明書のコンビニ交付サービスについてはこちらをご覧ください。
Q9:家系図を作りたいです。
自分で家系図を作るために戸籍を出す際は、まず誰のどこまでの戸籍が必要かを確認して、それに合わせて戸籍を出す必要があります。
一番初めに自分の戸籍を取っていただき、そこから父母・祖父母の戸籍へとさかのぼって取っていただく形になります。
ただし、戸籍は直系親族のみが請求できるものであるため、直系親族以外の戸籍を出す際は委任状が必要になることがあります。
Q10:筆頭者が亡くなったらどうなるのか。
筆頭者の方がお亡くなりになられても、戸籍の筆頭者は変わりません。
Q11:謄本と抄本の違いって何ですか?
謄本(とうほん=全部事項証明書)は、その戸籍に入っている方全員の記載があるもので、抄本(しょうほん=個人事項証明書)は指定された一部の方のみが記載されたものになります。
Q12:親子であるという証明をするために何を取ればいいのか。
ご自分の戸籍を取っていただくことで親子である証明ができます。
同じ戸籍であれば、戸籍謄本を取っていただくことで父・母・子の記載があります。
親子で戸籍が違う場合、お子様の戸籍を取っていただくと、父・母の欄にご両親のお名前及び続柄の記載があります。
Q13:戸籍の証明書には有効期限がありますか?
自治体では有効期限を設けておりませんので提出先の判断になります。
一般的には発行後3か月以内の証明書を指定する機関が多いようですが、ご提出先にお問い合わせください。