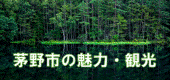本文
国保の医療費の自己負担限度額等について
国保における医療費の自己負担限度額等は、世帯主及び国保加入者の前年の収入・年齢・世帯構成等により決まります。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 総所得金額等(注1) |
自己負担限度額 |
自己負担限度額 「4回目以降」(注2) |
|
|---|---|---|---|---|
|
住民税 |
ア | 901万円超 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 | |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
| 世帯主及び国保加入者が住民税 非課税の世帯 |
オ | - | 35,400円 | 24,600円 |
(注1) 総所得金額等=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
(注2) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
70歳以上75歳未満の方の自己負担割合と限度額(月額)
| 自己負担割合 | 所得区分 | 該当条件 | 外来(個人単位)【A】 | 外来+入院(世帯単位)【B】 |
|---|---|---|---|---|
| 3割 | 現役並み 所得者3 |
住民税課税所得690万円以上 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% 【140,100円】(注1) |
|
| 現役並み 所得者2 |
住民税課税所得380万円以上 | 167,400円+(医療費費の総額-558,000)×1% 【93,000円】(注1) |
||
| 現役並み 所得者1 |
住民税課税所得145万円以上 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 【44,400円】(注1) |
||
| 2割 | 一般 | 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 | 18,000円 (注3) | 57,600円 【44,400円】 (注1) |
| 低所得者2 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 低所得者1以外 |
8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者1 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 各所得(注2)が0円 |
8,000円 | 15,000円 | |
- (注1) 過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
- (注2) 年金の所得は控除額を80万円として計算。給与所得からさらに10万円を控除して計算。
- (注3) 外来分のみ、年間(8月~翌年7月)の限度額(144,000円)が定められています。
70歳以上75歳未満の被保険者は、所得などに応じて医療費の自己負担割合が3割の「現役並み所得者」と2割の「一般」・「低所得者」に区分されます。
「現役並み所得者」の判定基準に当てはまる被保険者のうち、世帯の収入合計が一定の基準未満の場合は「一般」の区分となり自己負担割合が2割となります(収入等の情報が確認できないときは、申請が必要な場合があります)。
この収入額の判定には、確定申告した場合の株式等の譲渡等の収入を含みます。
※株式等の譲渡所得等を確定申告する方はご注意ください。
上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するため確定申告をした場合、自己負担割合の判定に用いる収入額には、株式の譲渡益ではなく売却代金が用いられます。
そのため、市・県民税の課税所得が145万円以上となる被保険者の方で、株式譲渡益がマイナスとなったことによる損失等の申告をした場合、収入額としてはプラスの金額が生じることとなります。
このような場合は「一般(自己負担割合2割)」の要件には該当せず、「現役並み所得者(自己負担割合3割)」のままとなってしまう可能性があります。
特定疾病療養受給者証をお持ちの方
特定疾病療養受給者証について をご覧ください。