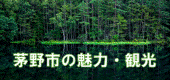本文
国保被保険者が高額な医療費がかかるとき2
高額医療・高額介護合算制度について
国保の医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額(8月~翌年7月)を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が支給されます。
申請書は、茅野市(国保保険者)より該当する方へ送付します。
詳しい内容は下記担当までお尋ねください。
限度額について
70歳未満の人がいる世帯
| 所得区分 | 限度額 | ||
|---|---|---|---|
| 住民税 課税世帯 |
所得901万円超 | ア | 212万円 |
| 所得600万円超901万円以下 | イ | 141万円 | |
| 所得210万円超600万円以下 | ウ | 67万円 | |
| 210万円以下 | エ | 60万円 | |
| 住民税非課税世帯 | オ | 34万円 | |
※ 所得=総所得金額(収入総額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)
70歳以上75歳未満の人がいる世帯
| 所得区分 | 該当条件 | 限度額 |
|---|---|---|
| 現役並み 所得者3 |
住民税課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 現役並み 所得者2 |
住民税課税所得380万円以上 | 141万円 |
| 現役並み 所得者1 |
住民税課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 一般 | 住民税課税所得145万円未満で、低所得者1、2以外 | 56万円 |
| 低所得者2 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 低所得者1以外 |
31万円 |
| 低所得者1 | 世帯主及び国保加入者が住民税非課税で、 各所得(※1)が0円 |
19万円 |
※1 年金の所得は控除額を80万円として計算。
※2 低所得者1の方で介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。