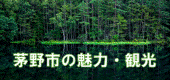本文
国保被保険者が柔道整復師(整骨院・接骨院等)の施術を受けるとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)について
柔道整復師とは、大学受験の資格がある者が、3年以上国が認定した学校や大学で専門知識を修得し、国家試験に合格した資格取得者です。整骨院・接骨院は、その柔道整復師が施術を行う施設です。医療機関(病院、診療所など)ではないので、診療の目的をもったレントゲン検査を行ったり、外科手術を行ったり、薬を投与することはできません。
整骨院や接骨院は、患者に代わって国保の給付(療養費)を保険者に請求する「受領委任」が認められています。そのため、患者は療養費の請求を整骨院や接骨院に委任すれば、保険医療機関で受診するのと同様に、窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示し、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合がほとんどです。
国保を扱っていない整骨院や接骨院において施術を受ける場合、療養費の支給を受けるには、市役所窓口にて療養費の支給申請をしていただく必要があります。申請方法については、国保の療養費について をご覧ください。
整骨院・接骨院等で国保を使えるとき
国保を使用して柔道整復師の施術が受けられるのは、外傷性が明らかな負傷(骨折や脱臼、捻挫、打撲、挫傷など)に限られます。
なお、骨折・脱臼については、あくまでも応急処置として認められた場合に限られ、応急処置後の施術には医師の同意が必要です
以下のような場合は、国保を使うことはできません。
- 仕事や家事などの日常生活による単なる疲れ、肩こり、腰痛、体調不良などに対する施術
- スポーツによる筋肉疲労、負傷原因が不明の筋肉痛に対する施術
- 打撲、捻挫が治ったあとの漫然とした施術、症状の改善の見られない長期漫然とした施術
- 外科・整形外科等で治療を受けている、同時期に同じ治療個所について柔道整復師に受ける施術
- 数年前に治癒した箇所が自然に痛み出したもの等
- 負傷原因が労働災害・通勤災害に該当するもの(労災保険の対象)。
国保を使用して施術を受けるときの注意点
国保を使用して柔道整復師の施術を受けるときには、次のことにご注意ください。
- 負傷の原因を正確にきちんと伝えて、保険の対象となるかどうか確認しましょう。
- 自己負担金の領収書並びに施術明細書を必ず発行してもらい、受診記録を控えておきましょう。
- 施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう。
- 交通事故の場合は、保険者に連絡することが必要です。
- 同一の負傷について、同時期に柔道整復師と医師に重複してかかることはできません。ただし、負傷の状態の確認のために定期的に医師の検査を受ける場合や、継続して施術が必要かについて確認するために医師の診察を受けて、施術を受けることは可能ですので、このような場合は医師の指示を得てその旨を柔道整復師に申し出てください。