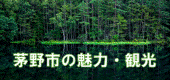本文
茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例
“茅野市の宝”である子ども達の健やかな成長を願い、平成25年1月1日に「茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例」が施行されました。
条例制定の背景
『茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例』は、子どもとその家庭を支援・応援することについて、基本理念を定めて、安心して子どもを生みまたは育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環境を整備して、子どもの未来に夢や希望が持てる社会の実現を目的としています。
茅野市では、平成14年7月に「どんぐりプラン(茅野市こども・家庭応援計画)」、平成22年10月には、「第2次どんぐりプラン」を策定し、茅野市の子どもたちが「たくましく・やさしい・夢のある子ども」に育つよう、市民のみなさんと行政が協働して計画の推進に取り組んできました。
取り組みを進めていく中で、どんぐりプランを継続して推進していくための裏付けとなる条例や、子育てと教育に関することの施策を一元的、一体的に推進するための基本となる条例が必要となりました。
茅野市こども・家庭応援計画(どんぐりプラン)については、こちらからご覧いただけます。
茅野市こどもに係る基本条例検討委員会
「茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例」の制定にあたっては、市民を交えた検討委員会を設置し、地域ぐるみで子育てを推進していくため、ご意見を条例に反映させるよう取り組みました。
条例の内容
前文
私たち市民は、次代を担う子どもたちが、
「少しの困難にあってもへこたれない、たくましく生きる力を持った子ども」
「命を大切にして、相手のことを思いやれるやさしい心を持った子ども」
「一人ひとりが自分の夢を持って、それに向かって努力する子ども」
に育ってほしいと願っています。
そのために、私たちは、子どもたちが茅野市の豊かな自然と文化の中で様々な体験を積み、
人と人との交流を通してお互いの個性を認め合い、生きる力と感謝の心を育んでいくことを応援します。
さらに、子育てに責任を持って関わることで、親や周りの大人も成長し、
大きな喜びや感動を得ることが大切なことだと考えます。
すべての市民が、安心して子どもを生み育てることができるまちづくり、
少年・少女時代を過ごせてよかったと思えるまちづくりを進めます。
ここに、茅野市民の宝である子どもたちが、
「たくましく、やさしい、夢のある子ども」に育つことを願い、この条例を制定します。
前文には、この条例の必要性とねらいなどの要素を記載しています。今後のまちづくりを進めるための、市民の、「願い」「応援」「考え」について明記しています。
また、「どんぐりプラン(茅野市こども・家庭応援計画)」の基本理念とする「たくましく、やさしい、夢のある子ども」への願いです。
条例の基本理念
次に掲げる事項を基本として子どもとその家庭を支援・応援します。
学ぶ
子どもの権利と利益を尊重して、学習・体験等を通じて人格の形成に取り組むこと。
支える
子どもと子どもを生み育てようとする人に必要なサービスの充実に向けて取り組むこと。
つなぐ
保健、医療、福祉、保育、教育その他の子どもに関するあらゆる分野において、相互に連携して協力すること。
親育ち
保護者が子育ての最も重要な責任を有するとの認識の下に、子育ての意義について理解して、子育てに伴う誇りや喜びをより深められるようにすること。
条例全文
茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例
目次
- 前文
- 第1章 総則(第1条-第3条)
- 第2章 子どもを育むための役割(第4条-第9条)
- 第3章 子ども及びその家庭への支援及び応援(第10条-第20条)
- 第4章 計画の策定及び推進(第21条・第22条)
- 第5章 こども・家庭応援会議(第23条-第27条)
- 第6章 雑則(第28条)
- 附則
私たち市民は、次代を担う子どもたちが、
「少しの困難にあってもへこたれない、たくましく生きる力を持った子ども」
「命を大切にして、相手のことを思いやれるやさしい心を持った子ども」
「一人ひとりが自分の夢を持って、それに向かって努力する子ども」
に育ってほしいと願っています。
そのために、私たちは、子どもたちが茅野市の豊かな自然と文化の中で様々な体験を積み、
人と人との交流を通してお互いの個性を認め合い、
生きる力と感謝の心を育んでいくことを応援します。
さらに、子育てに責任を持って関わることで、親や周りの大人も成長し、
大きな喜びや感動を得ることが大切なことだと考えます。
すべての市民が、安心して子どもを生み育てることができるまちづくり、
少年・少女時代を過ごせてよかったと思えるまちづくりを進めます。
ここに、茅野市民の宝である子どもたちが、
「たくましく、やさしい、夢のある子ども」に育つことを願い、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、子ども及びその家庭を支援し、及び応援することについて、基本理念を定め、安心して子どもを生み、または育てることができ、かつ、子どもが健やかに成長できる環境を整備し、もって子どもの未来に夢や希望が持てる社会の実現に役立てることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところによる。
- 市民 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者または市内に滞在する者をいう。
- 子ども 市民のうちおおむね18歳以下の者をいう。
- 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。
- 事業者 市内で事業を行う個人または法人をいう。
- 支援 市が子どもを育むための政策を総合的かつ計画的に実施することをいう。
- 応援 市、市民、地域、事業者等(以下「市等」という。)が相互に連携して、子どもを育むための取組を実施することをいう。
(基本理念)
第3条 市等は、次に掲げる事項を基本として子ども及びその家庭を支援し、及び応援するものとする。
- 子どもの権利及び利益を尊重し、学習、体験等を通じて人格の形成に取り組むこと。
- 子ども及び子どもを生み、または育てようとする者に必要なサービスの充実に向けて取り組むこと。
- 保健、医療、福祉、保育、教育その他の子どもに関するあらゆる分野において、相互に連携し、及び協力すること。
- 保護者が子育ての最も重要な責任を有するとの認識の下に、子育ての意義について理解し、子育てに伴う誇り及び喜びをより深められるようにすること。
第2章 子どもを育むための役割
(市の役割)
第4条 市は、前条の基本理念に基づき、子ども及びその家庭への支援を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 市は、前項の規定による支援をするに当たっては、保護者、学校等(保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校をいう。以下同じ。)、地域の住民、地域の関係団体、事業者その他の市民との総合的な調整を行うことにより、協力体制を構築するものとする。
3 市は、前項の規定による調整に当たっては、必要に応じて国及び長野県に協力を求めるものとする。
(保護者の役割)
第5条 保護者は、子どもが育ち、人格を形成する上で最も大きな役割を担っていることを自覚し、子どもとのふれあいを大切にし、自らが子育ての意義について理解を深め、子育てに伴う誇り及び喜びをより深められるように努めるものとする。
2 保護者は、子どもが基本的な生活習慣、社会の規範を守る意識及び善悪の判断を身に付けることができるように自らが範を示すとともに、豊かな人間性を育むことができるように努めるものとする。
(学校等の役割)
第6条 学校等は、集団生活を通じて、社会性、基礎学力、考える力、創造力等を子どもの心身の発達に応じて身に付けさせることができるようにするとともに、子どもが自ら学び、遊び、夢を持って将来への可能性を開いていくために、子育てをしている家庭及び地域と協働して教育を推進するものとする。
2 学校等は、積極的に教育活動等の内容を公表し、地域に開かれた体制の整備及び地域との協働による運営に努めるものとする。
(地域の役割)
第7条 地域の住民及び地域の関係団体は、子育てを地域全体で取り組まなければならない課題と捉え、子ども及びその家庭を応援することに積極的に関わり、地域の中で子どもが健やかに育つ環境づくりに努めるものとする。
(市民の役割)
第8条 市民は、安心して子どもを生み、または育てることができる社会の実現に役立てるため、あいさつの励行、地域の行事への参加等を通じて、良好な地域社会の形成に努めるものとする。
(事業者の役割)
第9条 事業者は、その雇用する労働者が子どもとの関わりを深めることができるように配慮するとともに、学校等または地域が行う職場体験活動その他の子どもの育成に関する活動に協力するように努めるものとする。
2 子どもを雇用している事業者は、その健康の保持及び成長に十分に配慮するものとする。
第3章 子ども及びその家庭への支援及び応援
(教育環境の整備)
第10条 市は、子どもが豊かな人間性を育み、たくましく生きる力を身につけることができるように、適切な教育環境の整備を推進するものとする。
(読書活動の推進)
第11条 市は、読書活動が子どもの豊かな心を育むために大切なものであり、かつ、生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることに鑑み、すべての子どもが自主的に読書活動を行うことができるように、その活動を推進するものとする。
(食育の推進)
第12条 市は、子どもが健全な食生活に必要な知識及び判断力を身につけるとともに、食に関する感謝の念や理解を深め、豊かな人間性を育むように、子育てをしている家庭、学校等及び地域において、食育の推進に努めるものとする。
(子どもの健康の保持増進)
第13条 市は、子どもの心身の健康の保持増進を図るため、健康教育、健康診査等の充実を図るものとする。
(子どもの社会参加の促進)
第14条 市は、子どもが社会の一員としての責任を果たせるように社会参加をする機会を拡充し、子どもの意見が適切に社会に反映される環境の整備に努めるものとする。
2 市は、子どもの個性を伸ばし、人間性を豊かにする文化的・社会的活動に子どもが参加し、体験することができる場を確保するように努めるものとする。
(福祉意識の醸成)
第15条 市は、子どもがすべての人を思いやる心を育むことができるように福祉意識の醸成に努めるものとする。
(子どもに安心・安全なまちづくりの推進)
第16条 市は、子どもが緑あふれる恵まれた自然に囲まれ、健やかな成長ができ、かつ、安心して過ごすことができるまちづくりを推進するものとする。
2 市は、子どもを犯罪、交通事故、いじめ、児童虐待等の被害及び子どもを取り巻く有害な環境から守る活動等の推進により、子どもが健やかに成長することができる安全で良好な環境づくりに努めるものとする。
(子育てをしている家庭への支援)
第17条 市は、保護者の多様な就労形態に対応するとともに、積極的な社会参加を支援し、並びに仕事及び子育ての両立を図るための総合的な施策を推進するものとする。
2 市は、子育てに関する多様な需要を的確に把握し、必要な保育サービス、放課後における児童の健全育成を図る事業等を実施するものとする。
(相談体制の充実)
第18条 市は、子どもに関する相談を行う機関、市民団体等と密接に連携し、子どもの健やかな成長及び子育てに関する総合的な相談の体制の充実を図るものとする。
(市民等の応援)
第19条 保護者、学校等、地域の住民、地域の関係団体、事業者その他の市民は、市の行う支援に協力するよう努めるとともに、それぞれの役割に応じ、子どもを育むための取組を行うものとする。
(連携及び協働)
第20条 市等は、子ども及びその家庭を支援し、及び応援するため、それぞれの取組を行うに当たっては、相互に連携し、及び協働して行うものとする。
第4章 計画の策定及び推進
(計画の策定等)
第21条 市は、子ども及びその家庭を支援し、及び応援することに関する計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
2 市は、計画の策定に当たっては、企画・立案段階から市民の参画により策定するものとする。
3 市は、計画を策定したときは、早くに、これを公表しなければならない。
4 市は、計画を効果的に推進するため、その評価を行い、必要があると認めるときは、見直しをするものとする。
(ネットワークの構築)
第22条 市等は、子ども及びその家庭を支援し、及び応援するためのネットワークを構築し、計画を推進するものとする。
第5章 こども・家庭応援会議
(設置)
第23条 子ども及びその家庭を継続的に支援し、及び応援するため、茅野市こども・家庭応援会議(以下「応援会議」という。)を設置する。
(任務)
第24条 応援会議は、次に掲げる事務を行う。
- 第21条の規定に基づき策定された計画の推進に関し必要な事項を調査し、及び審議すること。
- 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条に定める事務に関すること。
(応援会議の組織等)
第25条 応援会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
- 関係市民団体を代表する者
- 学識経験者
- 関係行政機関の委員または職員
- その他市長が必要と認める者
3 委員(前項第3号の委員を除く。)の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 前項の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 応援会議に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。
6 会長は、会務を総理する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 応援会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
(専門委員会)
第27条 応援会議に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
第6章 雑則
(委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に策定され、運用されている茅野市こども・家庭応援計画については、第21条の規定に基づき策定されたものとみなす。
(茅野市青少年問題協議会条例の廃止)
3 茅野市青少年問題協議会条例(昭和56年茅野市条例第30号)は、廃止する。
「茅野市たくましく・やさしい・夢のある子どもを育む条例」は下記からご覧いただけます