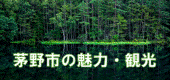本文
第4回コミュニティースクール運営委員会
令和4年度 第4回湖東コミュニティスクール運営委員会を開催しました
2月16日(木曜日) 第4回運営委員会での話題
(1)学校評価について
(1)校長より
よい評価「学校は,学校だより等で様子を伝えている」「学習していることがわかる」「先生は子ども達のがんばりをみとめている」今後も継続していきたい。
課題 CD評価が10%以上のもの
・あいさつ「自分から」4割の保護者があまりできていないと捉えている(課題)
・あいさつ以外にも学校としての課題
「子どもの話に耳を傾ける」
「子ども達を理解して学級づくりをしている」
「保護者や地域の声に耳を傾け,ともに考えようとしている」
「地域の人材を活用」
(2)教頭より
・読書に関わる声をたくさんいただいた。もっとよくするために何が必要か関心をもってくださっていることを感じる。
・願う子どもの姿についても把握できた。いかしていきたい。
・学校関係者評価報告(CS委員の評価)報告
特にあいさつは,自分からできる姿を目指していきたい。
(3)委員の皆さんからのご意見
・他校では朝「あいさつ運動」をやっている。湖東小ではどうか。
(校長)やってはいる。しかし不十分。児童会長とも方針を話し合った。あいさつを返してくれない児童が1割はいる。「よさたなほし」のあいさつを繰り返しよびかけ。
・評価の厳しい項目は,期待の表れ。より掘り下げ,具体的に提案を。
・学校からのおたよりが配信になると,地域の方が目にする機会が減る。紙も残してほしい。You Sayポストも子ども達の関心高い。すぐに読んでいる。紙代が厳しければ「女神の里」予算を。(加賀美地区コミュニティセンター所長)「女神の里プラン」補助金4月申請。
・わくわく講座10年以上 講師を校外から招いていることが湖東小のよいところ
子どもの頃の体験(例:凍み大根づくり)は将来役立つ。わくわく講座の郷土料理は好評。
今後も,地域の人たちとの交流をしながら継続していきたい。
・本校の不登校傾向の子について
評価がCDになりがちな項目(家庭内のこと)はデリケートで答えにくい。
課題が見えてくるような,より客観的な言い回しを。
・我が家の子ども達は,学校に愛着と誇りを持っている。感謝。自分のクラスがいかに素晴 らしいか,演説を聞いてもらいたいほど。
保護者の考え,子どもの姿を知るよい機会。年を追うごとに評価が上がっている項目は, 学校の取り組みが実ってきている証。
学校関係者評価8「学校は,地域の方にとって楽しみになるような開かれた場所になっている。」は低め。「楽しい」を含め,親しみの持てる学校に。
(2)家庭教育部会の振り返り
(1)学校からの要望 LINEを利用して応えた
(2)相談受付 You Sayポスト
(3)委員の皆さんからのご意見
・「質問」「おすすめ」等返事ができるよう依頼。回答する人の幅をさらに広めたい。
・この頃は命に関わる質問多い。様々な方に依頼したい。
この件について,図書館細川先生が命に関わる本(子どもにとってわかりやすい本)をそろえてくれた。おすすめの本があったら要望してほしいと言ってもらっている。
・お返事号のボリュームがかなりのページになる。印刷の負担が心配。親子ともに読めるよう発信の方法を考えてほしい。
・回答をCSのメンバーに依頼することも考える。
(4)CSだより 今年度2回発行
(5)学習支援 ミシンやわくわく講座等で成果大。さらに増やしたい。
(課題)地域での教育活動にどう結びつけるか?
(6)防犯ボランティア 3月終わりに新名簿作成 引き受け手募集を各地区に依頼
(7)たまてばこ できる回数が増えてよかった
(8)LINEグループ 活動を支えてくれる人探しやコロナ禍でもできることをやったことなど成果は大きい。今後も地区との協働を考え,活動を推進。さらに多くのメンバー加入を希望。
その他
・昨年度よりも活動しやすくなっている。地域との結びつきが強い学校。
・コロナ禍で活動しにくかっただろうが,工夫して活動。継続してさらに形に
職員より
・凍み大根でお世話になった。これによって,来年度わくわく講座で郷土料理希望する子どももいる。
・来入児のかざぐるま拾い(運動会)中止 1月の一日入学で1年生と交流予定したが延期。ここへきて警戒レベル下がったのでこれから交流。入学に希望持てるようにしたい。
研究は,「子どもが学びを深めるためにどうするか」すすめてきた。来年度は「考える子」を中心に据え,学びを実感できるようにしていきたい。(職員 臼田)
・米作り 困ったときに支えてくれたことに感謝。学校と地域との連携を感じた。
・地域と密接につながっていることを感じ,安心した。継続してほしい。
思ったような活動ができないが,コロナのせいにしているわけにはいかない。今後インフルエンザのような扱いになっていくか。これから盛り上げていくためにどうすればよいか。