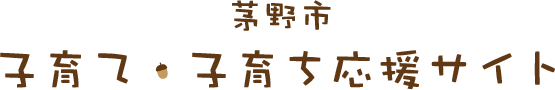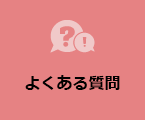子育て世帯の方へ 福祉医療費給付金制度に関する よくある質問(FAQ)
福祉医療給付金、こどもの医療費助成に関するよくある質問と回答(FAQ)です。
Q2. 県外の病院にかかったり、受給者証を出し忘れたりした場合はどうなりますか?
Q3. 対象となるのはどんな子どもですか? 年齢制限はありますか?
Q5. 薬局ではいくらかかりますか?入院中の食事代はどうなりますか?
Q6. 受給者証を出し忘れました。あとから手続きできますか?
Q8. 園や学校でけがをして、スポーツ保険を使う予定です。福祉医療費も使えますか?
Q12. 窓口で500円以上払いました。間違いですか? 戻ってきますか?
Q13. 受給者証をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
Q14. 健康保険証が変わりました。何か手続きが必要ですか?
Q15. 振込先の口座を変更したいです。どうすればいいですか?
Q17. 保険証を持たずに診療を受け、いったん全額自己負担した場合はどうなりますか?
Q18. 治療用装具や眼鏡を作った場合は、福祉医療費の対象になりますか?
Q19. 八十二銀行と長野銀行の合併に伴い、口座番号が変わるそうですが、手続きは必要ですか?
Q20. スポーツ保険を申請していましたが対象になりませんでした。福祉医療は使えますか?
Q21. 子どもが高校3年生ですが、受給者証の有効期限が年度末より前に切れてしまいました。どうすればよいですか?
関連情報
Q1. 福祉医療費助成って、どんな制度ですか?
A. お子さんの医療費の自己負担を、1か所あたり月500円までに抑える制度です。
長野県内の病院や薬局で「保険証」と「受給者証」を提示することで、1医療機関ごとの自己負担が月500円で済みます。
Q2. 県外の病院にかかったり、受給者証を出し忘れたりした場合はどうなりますか?
A. 後日、申請することで自己負担の一部が戻る場合があります。
以下のような場合は、領収書を添えて市役所で申請してください(郵送・電子申請も可能です)。
申請期限は、診療月の翌月1日から2年間です。
- 県外の医療機関で受診した
- 受給者証を提示しなかった
- 医療機関側が新方式に対応していなかった
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
Q3. 対象となるのはどんな子どもですか? 年齢制限はありますか?
A. 高校3年生になる年度末までの子どもが対象です。
一般の子どもは「18歳に到達する年度の3月末」まで自動的に対象となります。
ただし、ひとり親家庭の子どもは「18歳の誕生月末(1日生まれは前月)」でいったん終了し、在学証明書の提出により年度末まで延長されます。
Q4. 病院代はぜんぶ無料になるんですか?
A. 自己負担は「1か所ごとに月500円まで」です。
たとえば、同じ月に、小児科と歯科を受診した場合、それぞれで500円の負担が発生します。
また、入院と外来も別の医療機関扱いとなるため、500円ずつかかります。
Q5. 薬局ではいくらかかりますか?入院中の食事代はどうなりますか?
A. 病院とは別に、薬局でも500円の負担があります。
薬局が同じでも、処方元の医療機関が異なれば、それぞれ500円ずつ必要です。
また、入院中の食事代(食事療養費)も福祉医療費の対象です。
Q6. 受給者証を出し忘れました。あとから手続きできますか?
A. できます。領収書を添えて市役所で申請してください。
保険課(1階8番窓口)、または郵送・電子申請でも受け付けています。
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
※申請が必要な場合の期限は、診療月の翌月1日から2年間です。
Q7. 医療費はいつ振り込まれますか?
A. 通常は、診療月の約2か月後の月末に振り込まれます。
振込名義は「チノシイリョウヒ」と表示されます。
処理状況によっては遅れる場合もあります。
Q8. 園や学校でけがをして、スポーツ保険を使う予定です。福祉医療費も使えますか?
A. 原則として、スポーツ保険が優先されます。
福祉医療費受給者証を使ってしまうと、重複給付となり、返還をお願いすることがあります。
Q9. 引っ越す予定です。手続きは必要ですか?
A. 茅野市から転出する場合は、受給者証を必ず返却してください。
転出先では使用できません。
返却がないまま使用した場合、給付分の返還をお願いする場合があります。
Q10. 振込口座や保険証が変わったら?
A. 市役所への届出が必要です。
変更内容が確認できるもの(通帳・新しい保険証など)をご用意のうえ、保険課(1階8番窓口)で届け出てください。
郵送・電子申請でも手続き可能です。
電子申請はこちら(受給資格等変更届<外部リンク>)
Q11. すべての医療費が対象になりますか?
A. 保険適用外の費用は対象外です。
対象外の例:健診料、予防接種、薬の容器代、個室料、文書料など。
Q12. 窓口で500円以上払いました。間違いですか? 戻ってきますか?
A. ケースによりますが、申請により戻る場合があります。
以下のような場合が考えられます:
- 保険がきかない費用を含んでいた場合 → その分は対象になりません(例:健診料、予防接種、文書料、差額ベッド代など)
- 窓口で受給者証を提示せず、通常の自己負担額を支払った場合 → 領収書を添えて申請すれば、超過分が戻る可能性があります
- 県外の医療機関で受診した → 申請により給付対象となります
まずは領収書をご確認ください。
なお、同じ病院でも、医科と歯科を受診した場合や、外来と入院がある場合は、それぞれで500円の負担が必要です。
また、薬局の場合は、処方せんを発行した医療機関ごとに500円の負担が必要です。
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
※申請が必要な場合の期限は、診療月の翌月1日から2年間です。
Q13. 受給者証をなくしてしまいました。どうすればいいですか?
A. 市役所で再交付の手続きができます。
保険課(1階8番窓口)、または郵送・電子申請で申請してください。
電子申請はこちら(受給者証再交付申請<外部リンク>)
Q14. 健康保険証が変わりました。何か手続きが必要ですか?
A. はい。新しい保険証の内容に基づき、届出が必要です。
保険課(1階8番窓口)または郵送・電子申請で手続きしてください。
電子申請はこちら(受給資格等変更届<外部リンク>)
Q15. 振込先の口座を変更したいです。どうすればいいですか?
A. 口座変更の届出が必要です。
保険課(1階8番窓口)、または郵送・電子申請で手続きできます。
電子申請はこちら(受給資格等変更届<外部リンク>)
Q16. 入院した場合はどうなりますか?
A. 入院についても、外来と同様に福祉医療費の助成対象になります。
自己負担は「1か所ごとに月500円まで」です。
入院・外来はそれぞれ別の医療機関扱いとなるため、同じ病院でも入院と外来でそれぞれ500円ずつかかります。
また、入院中の食事代(食事療養費)も対象となります。
ただし、保険がきかない費用(差額ベッド代、文書料など)は対象外です。
Q17. 保険証を持たずに診療を受け、いったん全額自己負担した場合はどうなりますか?
A. この場合でも、最終的に自己負担分から500円を超えた分は福祉医療費で戻ります。
まずは、加入していた健康保険から「療養費」として払い戻しを受けてください。
保険証を提示しなかったために10割負担(全額自己負担)となった場合でも、健康保険組合や国民健康保険などの保険者に申請すると、本来の自己負担分(2~3割)を除いた金額が払い戻されます。
次に、福祉医療費給付金について申請してください。
対象となる自己負担分から、500円を超えた分が戻ります。
領収書や保険者からの支給決定通知を添えて、市役所に申請してください。
郵送・電子申請も可能です。
- 注意点
保険者への療養費申請には領収書の原本を提出します。
福祉医療費給付金の申請にも領収書が必要になるため、必ず事前にコピーを取ってから提出してください。
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
Q18. 治療用装具や眼鏡を作った場合は、福祉医療費の対象になりますか?
A. はい、対象になります。
治療用装具(コルセット・足底板など)や、斜視・弱視などで医師が必要と認めた治療用眼鏡は、健康保険の「療養費」として扱われます。
まずは、加入している健康保険に申請して払い戻しを受けてください。
その後、自己負担分から500円を超えた分が福祉医療費から戻ります。
市役所への申請の際には、医師の指示書(診断書・装具作成指示書など)、領収書や保険者からの支給決定通知を添えて、市役所に申請してください。
郵送・電子申請も可能です。
- 注意点
保険者への療養費申請には医師の指示書および領収書の原本を提出します。福祉医療費申請でも医師の指示書および領収書が必要となるため、必ずコピーを取ってから提出してください。
医師の指示がない「おしゃれ用の眼鏡」など、健康保険がきかないものは対象外です。
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
Q19. 八十二銀行と長野銀行の合併に伴い、口座番号が変わるそうですが、手続きは必要ですか?
A. 手続きは原則不要です。
令和8年(2026年)1月1日に、八十二銀行と長野銀行が合併し、新しい銀行名は「八十二長野銀行」となります。
現在、福祉医療費給付金の振込口座として長野銀行の口座を登録されている方は、合併により店番号や口座番号が変更となりますが、銀行側で自動的に新しい口座へ読み替えて振込が行われるため、市への届出や手続きは不要です。
八十二銀行の口座を登録されている方は、合併後も店番号と口座番号の変更はありませんので、市への届出や手続きは不要です。
■ 届出を希望される場合
ご希望の場合は、口座変更届を提出いただくことも可能です。
届出は、窓口・郵送・電子申請のいずれでも行えます。
電子申請はこちら(受給資格等変更届<外部リンク>)
■ 他の機関からの振込について
本市からの福祉医療費給付金の振込については上記のとおり問題ありませんが、他の機関等からの振込については、自動読み替えの取扱いが異なる場合があります。
該当する場合は、振込元または金融機関へご確認ください。
Q20. スポーツ保険を申請していましたが対象になりませんでした。福祉医療は使えますか?
A. スポーツ保険(災害共済給付金)が適用される場合、福祉医療費は使用できません。
ただし、スポーツ保険の対象外となった場合は、福祉医療費給付金を申請できる可能性があります。
その場合、領収書を添えて市役所で申請してください。
保険課(1階8番窓口)、または郵送・電子申請でも受け付けています。
電子申請はこちら(福祉医療費給付金支給申請<外部リンク>)
Q21. 子どもが高校3年生ですが、受給者証の有効期限が年度末より前に切れてしまいました。どうすればよいですか?
A. 「母子・父子家庭等」の方の受給資格は、通常、子どもの18歳の誕生日月(1日生まれは前月)の月末日までですが、子どもが高等学校等に在学している場合、在学証明書を提出することで卒業まで受給資格を延長できます。
在学証明書を提出しない場合は、18歳の誕生月末日で資格が終了しますが、「こどもの医療費助成」の受給資格を手続きすることで、18歳年度末まで現物給付の受給者証を使用できます。
在学証明書の提出による延長手続きは、保険課(1階8番窓口)または郵送・電子申請で受け付けています。
電子申請はこちら(在学証明の提出<外部リンク>)
※電子申請により受給資格を延長した場合、受給者証は受給者本人の住民登録の住所へ1週間程度で郵送されます(送付先変更届を提出されている場合は、変更後の住所へ郵送されます)。
お急ぎの場合は、保険課窓口で即時発行しますので、窓口にお越しください。
※こどもの医療費助成の手続きは窓口で申請が必要です。