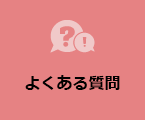「縄文」を活かしたまちづくりとは
「縄文」でまちづくりはできるのか?
縄文と聞いても、あまりにも昔過ぎてどのような時代であったか想像しづらかったり、「原始的」や「泥臭い」イメージがあったりして、「縄文」という響きに魅力を感じる人はあまり多くないと思います。
そのような「縄文」で、まちづくりはできるのか?
また、そもそも「縄文」でまちづくりとは何なのか?と誰しもが疑問に思うのではないでしょうか。
縄文プロジェクトの背景
日本が縄文時代の頃、世界では多くの地域で農耕と牧畜の社会から文明への時代へと進み始めていました。
ヨーロッパ文明や中国文明は大陸を基盤としていることから、自然と対峙し克服しようとする文明であり、特にヨーロッパ文明は排他的な要素を持ち、自然を破壊しながら世界的規模で拡大してきました。
一方、縄文文化は約1万年に渡り続いた平和な社会で、自然の生態系の中で共生し、調和した文化であったことから、ヨーロッパ文明と対極のものであったと言えます。
しかし、日本においても縄文時代を境に、自然と対話する文化から自然と対立する文化へと変わっていきました。
21世紀に入り、世界は自然破壊、環境汚染、地球温暖化をはじめとする様々な地球環境の危機や戦争などの問題に直面しています。
これらの問題に対し、自然保護や失った自然の回復、自然との共生を模索する動きが様々な分野に広がりをみせ、人類社会の目指すべき方向として、次第に世界の潮流になりつつあります。
このような背景から、人と自然が共生し、調和した縄文文化が世界からも注目されています。
日本人の文化の原点とも言える縄文人の社会のありようは、人類社会の目指すべき方向として道標になるのではないでしょうか。
縄文文化を形成した心
縄文プロジェクトの冒頭では、―今、なぜ、「縄文」か―と題して、「縄文」を活かしたまちづくりの必要性について触れています。
平和な年月が約1万年に渡り続くことができた縄文文化には、現代社会が抱える問題を解決する糸口があるのではないでしょうか。
その縄文文化を形成した縄文人の心は、次のようであったと考えられます。
- 約1万年にわたり続いた定住生活を可能にした支え合いや助け合いの生き方は、「友愛の心」を象徴しています。
- 食料にする木の実や住居の材に使用する林などを大切にし、自然を必要以上に壊さないという生き方は、自然と共生し「足るを知る心」を象徴しています。
- より豊かな生活を求めて交易を行い、東北や北海道まで黒曜石を運ぶなどの情報交換能力やフロンティア精神は「たくましさ・冒険心」を象徴しています。
- 草を縄にする、土を器にする、黒曜石から矢じりや刃物を創るなど、そこにある資源を上手に活用する知恵と工夫の生き方は、「創造の精神(ものづくりの心)」を象徴しています。
こういった心は、縄文人の「心」であると同時に、日本人が大切にしてきた「心」であり、日本人のDNAに深く刻み込まれたものであると思います。
近年、この心が忘れられつつあり、様々な社会問題が起こっていますが、もう一度この日本人が大切にしてきた心を見つめ直すことで、これらの問題を解決する糸口を見つけることができるのではないでしょうか。
茅野市に残る縄文遺産
今から約5,000年から4,000年前の縄文時代中期に、縄文文化が最も繁栄したとされています。茅野市ではこの縄文時代中期の遺跡が最も多く確認されており、他の縄文時代の遺跡と合わせるとその数は230ヶ所を超えます。
この遺跡のうち尖石遺跡は、遺跡の国宝と言われる国特別史跡に指定されています。国特別史跡は、四神の壁画で有名な「キトラ古墳」、「高松塚古墳」や、鹿苑寺(金閣寺)庭園、慈照寺(銀閣寺)庭園、江戸城跡などもあり、日本文化の象徴とされるものが指定されています。
また、土偶(縄文のビーナス)と土偶(仮面の女神)は、いずれも縄文時代の文化遺産として高い評価を受け国宝に指定されており、全国で複数の国宝土偶を所有するのは茅野市のみです。
このように、茅野市は他に類をみないほど縄文時代の遺産がある地域であり、これらの遺産は茅野市の宝であると同時に日本の宝であるとも言えます。
この宝を全国や世界に発信し、まちづくりに活かすことは、ごく自然なこととも言えるのではないでしょうか。
「縄文」を活かしたまちづくり
「縄文」を活かしたまちづくりとは、縄文文化の精神性を学び、その精神性を私たちの生活に取り入れる取組と、縄文遺産を活用した茅野市のイメージや雰囲気づくりにつながる取組であると考えます。
この2つを言い換えると、縄文文化を形成した縄文人の精神性を学ぶひとづくりと、この地域に残る縄文遺産を活かしたまちづくりです。
そして、「ひとづくり」と「まちづくり」を両輪とすることで、一過性ではない持続的な取組につながることが期待できます。